
Next-Generation Global Talent Program
山口浩輝氏(不二製油株式会社 研究開発本部 グローバル市場ソリューション部門)

『リーダーシップ・ラウンドテーブル』は、グローバル企業において、情熱と使命感をもって長期にわたり「人材育成」に貢献されているリーダーをゲストにお迎えし、弊社、揚石洋子と秋吉新平を交えた対談形式で、インタビューさせていただくシリーズ企画です。(この記事は、2021年3月に実施したインタビューをもとに構成したものです。)

日鉄ソリューションズ株式会社
人事本部 人材開発部 人材育成グループリーダー/アカデミーセンター 運営総括グループリーダー
鍬形佐和氏
鍬形さんにはじめてお会いしたのは、2016年でしたね。鍬形さんが入社された直後だったかと思います。当時、日鉄ソリューションズ(以降、NSSOL)人事の皆さんは、シンガポールで開催する採用イベント(Job Fair)の準備の真っ只中でいらっしゃったことを覚えています。Job Fairで、NSSOLの魅力を伝えるべく英語でプレゼンを準備されていたご担当者様に、フィードバック・セッションのデモをさせていただいたのがきっかけでした。
鍬形さんとは、グローバル人材についてお互いが思い描いている理想像も共通点が多く、お目にかかった当時から、お話していると自然と熱量が上がりました!前職で、鍬形さんがITトレーナーとしての経験を積まれてきたことも大いに関係していると思いますが、トレーニングの勘所やノウハウを熟知しており、シャープなビジネス視点で人材開発を推進されるプロフェッショナリズムを感じていました。
はじめてお会いした時から、揚石さんとは本当にお話が合いました。プラニングも対話を重ねながら、企画を具体化させていくことができました。こちらが求めていることを察知してくださっていたので、細かい説明は不要でしたね。揚石さんの存在感や、仲介しながら牽引するスタイルが印象的でした。揚石さんのもとで、Seven Seasのグローバルなメンバーがチーム一体となって、いきいきと仕事をされていましたね。

鍬形さんのこれまでのキャリアについてお話いただけますか。リーダー職に就かれるまでには、いろいろな局面でハードな体験も乗り越えられてきたのではないでしょうか。
日系SIerのSEとしてキャリアをスタートしました。3年の在籍期間中、後半は事業企画系のSE職を務めました。次第に、人材育成に関わる分野に携わりたいという思いから、別SIerのグループ会社である研修会社に転職しました。
7年間はIT講師を務めた後、自ら社内で企画部門を立ち上げ、研修の企画や広報を担当しました。この会社には、通算10年ほど勤務しましたが、最適な研修を一つ一つ提供するという意味で、都度都度の出会いが日常です。自分のキャリアの先を考えた時に、研修会社で従事できるショート・タームの仕事から、事業会社の経営戦略に根差したロング・タームの人材育成の仕事がしたいという思いが募り、NSSOLに転職しました。
入社当時のNSSOLの人事部、特に人材育成部門は、どちらかと言うとオペレーション志向の強い組織でした。私が目指していたのは、オペレーションではなく「経営と一体になった戦略的な人事」だったので、ここで焦点となる「人材の育成」について、人事部長と積極的にディスカッションをしました。当時のNSSOLの社風は、上司に直接意見を言うカルチャーではなかったので、入社早々、ストレートに意見をぶつけてくる私のような社員は、ある意味、浮いた存在だったかもしれません。
先ずは、上司や同僚との信頼関係の構築が何よりも大切だと思ったので、カジュアルに食事などを共にしながら、コミュニケーションを重ねました。NSSOLに入社する前に積み上げてきた人材育成に関する経験値や、課題認識、NSSOLの人材開発部門が今後向かうべき方向性などを共有していくうちに、チームとしての一体感が生まれてきました。かつては、情報が属人化していて、担当者に聞かなければ、研修の詳細がわからなかった状況も多々ありましたが、今では、チームで研修体系を明確にし「人材開発の見える化」が進んできています。
ロジックと感情の両面を一貫して大切にしてきた鍬形さんのリーダーとしてのご努力が、実を結んだんですね。
御社では、ミーティングにおける参画意識の変革など、ミーティング・マネジメントや異文化コミュニケーションをテーマにしたトレーニング・プログラムを継続的に実施させていただいていますが、具体的にどんな成果を感じていらっしゃいますか。
御社には、グローバルを切り口にしたトレーニングを依頼しましたが、実は、これは、私が常々「会議が変われば、日本の会社が変わる!」と考えてきたことから端を発しています。ともかく、会議において、タイムマネージメントが行われずに時間切れとなる会議が多いことに問題意識を感じました。また、会議中、何も発言しなくてもよいと思っている人がいたり、特定の人が場をしきっていた状況に、大きな違和感があったのです。Seven Seasの研修では、導入部分で、ミーティングの理想像と現実の姿を対比しながら、研修を進めていただきましたね。
グローバルという文脈に限定せず、広い意味で、ダイバーシティー&インクルージョンの取り組みはどのような状況でしょうか。
鍬形さんも女性の活躍という意味ではロールモデルでいらっしゃると思います。
現状としては、今、まさに、歩み続けているというところです。今後は、多様性を活かすための取り組みや啓蒙も、さらに強化していきたいと思っています。まだ、グローバル人材や、女性の管理職も多いわけではありませんが、管理職ポジションへの登用を含めて、積極的な取り組みが進んでいます。ラインを持っている女性のGL(Group Leader)は、まだ少数ですが、今後が期待されているところです。

NSSOLアカデミーについて、ご紹介いただけますか。
NSSOLアカデミーは、2014年に発足しました。弊社では部長相当の資格に昇進すると、仕組みとして、LP(リーディング・プロフェッショナル)の資格試験を受験します。LPの認定を受けたら、人材育成や後継者育成に資する活動を、自発的にワーキング・グループを作って活動することが求められます。NSSOLアカデミーは、バーチャル組織なので、LPの活動は、本業と並行して行われます。現在、私自身は、NSSOLアカデミー事務局のグループリーダーを務めています。
NSSOLアカデミーでは、 PM(プロジェクト・マネージャー)、ITモデリングなど、プロフェッショナル類型ごとに様々な教育プランを施策し、ラーニングの機会を提供しています。例えば取り組みの一つに 「PM駆け込み寺」があります。プロジェクトマネジメントに悩むプロジェクトマネージャーに対し、コーチング手法を用いて悩みの解消を促進しています。全6回で、回を重ねるごとに、癒し・共感・気づきを得るプロセスを特徴としています。
「PM駆け込み寺」ですか!炎上案件を含め過酷な環境下で力を尽くされているメンバーが駆け込めるというのは、本当に心強いサポートですね。今後はどのような展望を持たれていますか。
NSSOLアカデミーの価値観や取り組みは、とても意味があると感じています。ただ、全社員にこの取り組みが確実に伝わっているかというとそうでない部分もあると思います。そういう意味では、社内広報や全社施策との連携には、さらなる努力をしたいと思っています。
御社は、NSSOL社員のコンピテンシーとして「伝承力」を掲げられていますね。グローバルな社会で、ビジネスを発展させていく上で、御社が重視しているのは人間力なのではという印象を受けます。和の力と最先端技術の融合という魅力が大いに感じられます。
その通りですね。人をとことん大切にする。見捨てないと言う意味では、古き良き日系企業の文化を感じます。十分に能力が発揮できていないメンバーがいれば、上位のメンバーがとことん向き合い面倒を見るという文化が根強くあります。
人事面では、ポテンシャル人材の登用を含め、将来目線での戦略的人材育成を推進すべく、サクセッション・プランについても、各ファンクションが一体となって、積極的な取り組みを進めています。次なるステップに向けて、変革期を迎えていると感じます。
まさに、種を蒔いてきたからこそ今があるのではないでしょうか。

これからの時代のグローバル・コミュニケーターに求められる資質として、どのようなマインドセットやスキルが求められていると思いますか。これまで、弊社では、全身全霊でクライアント・ニーズにお応えしてきた結果、500以上の研修プログラムを開発してきました。その内容を、今一度立ち戻って分析した結果、グローバル・コミュニケーターに求められる50のコトが浮き彫りになりました。
私は、一人旅が好きで、ビジネス・トリップ以外に、これまで50カ国以上訪れています。Seven Seas の「グローバルコミュニケーターが実践している50のコト」を拝見して、1から6の6つのマインドセットについて、強い共感を覚えます。12の「出会ってすぐに打ち解け合う力」も大切ですね。
まず第一に、主張する意思、そして、相手の気持ちを受け入れ、現地のルールを守って振る舞うことの重要性です。グローバルな環境におけるコミュニケーション能力についてですが、単に外国語を話すということではなく、相手に、自分と話したいという気持ちになってもらうことがキーポイントで、これが抜けていると、言語能力に関係なく、いつまでたっても、話を聞いてもらえなくなります。
また、今後より一層求められるのは、変化に適応する力でしょうか。グローバルだからというわけではなく、VUCAの時代にキャッチアップできる力は必要だと思います。と同時に、変化を楽しみながらも、大切にしたい価値観や信条についてはブレない力を培うことがこれからは必要だと思っています。
好奇心も必要ですね。新しい変化に対して、諦めてしまうのではなく、好奇心を向けて知ろうとしたり、新しい発見を楽しめる力も大切ですね。
人材開発における今後の優先課題、またこれからSeven Seasに期待していることがあれば、お聞かせいただけますか?
中長期視点で、リーダーシップ研修やマネジメント研修などを中長期視点で企画していきたいと思っています。グローバルだからということではなく、人間のベーシックなところ、自分のあり方を探求するラーニング体験を英語でやっても面白いかなと思っています。新しい研修技法・アプローチとしても可能性を感じます。
最近、アサーティブ・コミュニケーションのトレーニングを、総合商社様向けに実施したのですが、同じ内容を日本語で展開すると、おそらく受講者はそれほど関心を示さない感じがするのですが、英語で実施することで、新鮮な学習体験となっていることがわかりました。英語環境という異界に入り込むと、学ぶスタンスが変わってくるのは面白いですね。また、「英会話の研修」だと気後れする人が多いのですが、英語で何かを学ぶということになると、すごくプラス思考になる人が多いのも不思議です。英語を学ぶのではなく、英語で学ぶという環境が求められていると思います。
まさに、その通りですね。ディズニーランドに行くと異空間でテンションが上がるように、英語環境になると、気分が上がってオープンになる日本人が多いような気がします。ちなみに御社のトレーニングは、トレーニングそのものも楽しいし、打ち合わせの時からワクワクします。私にとってセブンシーズは、共に想像力(創造力)を膨らませて、これからの人材育成を実現させるための大切なパートナーです。引き続き、クリエイティブで、プロダクティブな企画を共にプランしていけたら嬉しいです!
今回、リーダーシップ・ラウンドテーブルで鍬形さんのお話をうかがい、経営と人事が一体となった筋が通った方針をより深く理解することができました。これからも、良いプレッシャーをいただきながら、共に歩ませていただければと思います。

山口浩輝氏(不二製油株式会社 研究開発本部 グローバル市場ソリューション部門)

トヨタコネクティッド株式会社 戦略人事部
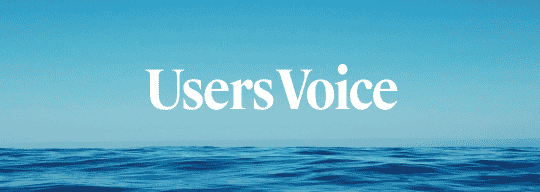
金融系企業 財務部門

林 和明氏(サントリーホールディングス株式会社 デジタル本部 デジタル戦略部 課長)

柏原千英氏(アジア経済研究所 学術情報センター長)

竹内洋二氏(日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 モビリティサービス事業本部長)

早崎達夫氏(積水フーラー株式会社 代表取締役副社長)
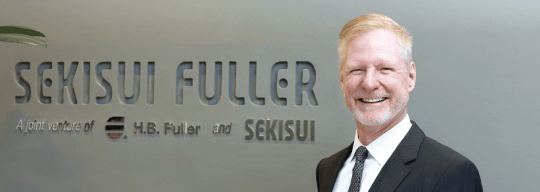
Mr. Scott Pergande氏(積水フーラー株式会社 代表取締役社長)