
Next-Generation Global Talent Program
山口浩輝氏(不二製油株式会社 研究開発本部 グローバル市場ソリューション部門)

『リーダーシップ・ラウンドテーブル』は、グローバル企業において、情熱と使命感をもって長期にわたり「人材育成」に貢献されているリーダーをゲストにお迎えし、弊社、揚石洋子と秋吉新平を交えた対談形式で、インタビューさせていただくシリーズ企画です。

久田氏をお迎えして、以下の3つのテーマでお話をうかがいました。
久田さんと初めてお目にかかったのは、2001年の春でした。新卒研修の現場に激励に来てくださったのを思い出します。
懐かしいですね。当時、マイクロソフトで人事本部長を務めていた頃ですね。
久田さんとの出会いは、20年以上も前になるのですが、それ以来、久田さんは、セブンシーズの中でもアイコニックな存在です。抜群の行動力と確固たる信念を持って、人と組織の成長のために奔走されている久田さんから、こうして、直接、お話をうかがう機会をいただけて、大変ありがたく思っています。これまで久田さんが歩まれてきたキャリアについて、教えてください。
新卒で、TERUMOに入社したのですが、いきなり人事部配属になりました。人事系のキャリアはここからスタートしたとも言えますが、その後、異動になった総務部では、従業員代表として団体交渉の経験を積みました。当時の労働組合長の目論見として、人事を経験したメンバーを労働組合に引き入れたかったという話も聞いています。
キャリアのスタートから、まさに人間力が求められるタフな経験をされていたんですね。
そうですね。人事とは真逆の立場で、しかも、自分はまだ20代でしたからね。年上の方々が多数いる場で、従業員代表としてどうリーダーシップをとっていくのか、どう集団を動かしていくのかが試されました。労働組合は労働者の利益を守るために大変厳しい視点で要求をあげてきますが、その要求をどれだけ会社にぶつけられるか、また会社と妥結した後に、協約を全国の組合員にどうやって下ろしていくか、そのあたりはタフでしたね。同じ集団を会社側から見ていくのと、被雇用者の連帯組織の側から見ていくという両方の経験が、今、思えば、自分のリーダーシップ・スタイルのベースになっているのかもしれません。
約7年間、人事・総務の経験を積んだ後、次のキャリアとして国際営業に興味があったので、社内異動の希望を出してみました。タイムリーに異動先のポジションも内定し、新たなチャレンジができるとモチベーションも上がっていたのですが、その矢先に、人事の幹部候補として管理部門に残って欲しいと、引き留められてしまったんです。自分にとっては、まさかの展開でしたね。結果として、私は、会社側の期待に応える道は選ばず、マイクロソフトへの転職を決めました。
IT業界に飛び込んだきっかけは、どんなことだったのでしょうか。
TERUMOの総務部で、OA化の推進を任されていたので、コンピューターに触れてITへの興味が広がりました。マイクロソフトに入社したのは、1988年の夏だったのですが、当時の社長の古川さんとの出会いもあり、マイクロソフト日本法人の基盤を一緒に作ろう!と勢いづけられたんですね。
まさに、日本マイクロソフトの幕開けの時代ですね。

「久田さん、ビルを探してくれ!」から全てが始まりました。そんな経験はないのに、ゼネコンの交渉からフロアレイアウト、物理的な配線、実際の引っ越し作業の手配などを行い、三番町から西新宿へ移転、さらには笹塚の新しいビルの契約までこぎつけました。その一方で、5年かけて人事・総務の基盤づくりをしました。1993年に成毛さんが社長に就任するタイミングで、今度は「テクニカル・サポートの体制をつくって欲しい」との特命を受けたんです。人事と総務の経験はあるものの、技術系ではなかったので、果たして自分が全うできる責務なのかと考えましたが、成毛さんは「とにかく、人材を集め、組織化し、集まったメンバーのモチベーションを高めることをやってもらいたい。久田さんならできる」と乗せられてしまったんです。Windows 3.1のリテール・パッケージ・リリースを目前にひかえていた状況で、時間的余裕は全くありませんでした。 R&Dの協力も得ながら、なんとかテクニカル・サポートの体制を立ち上げ、以来、Windows 95のリリースを経てWindows 98のリリースまで、約6年間、サポートの道で生きてきました。また、1999年には、2000年問題の統括責任者として、Y2Kをめぐる対応で社内をとりまとめ、外部の団体や公的機関などのディスカッションの場に呼ばれたり、テレビや新聞などメディアでの発信を積極的に行いました。
2001年に人事本部長に着任しました。その頃には、マイクロソフトにも多様な人材が集まるようになり組織規模も大きくなってきたので、管理職対象のトレーニングを全社展開し、マネジメント力の強化にフォーカスしました。3年後、そろそろ新しいことをやりたいと思っていた頃に、Xboxへの異動が実現したんです。当時、採用活動も積極的に行っていて、ストリート系ファッションに身を包んだ個性的な仲間たちと共に過ごしました。
Xboxのゲーミングのビジネスが、Kinectやホロレンズなど、マイクロソフトのテクノロジーの発展を促した功績は大きいのではないでしょうか。久田さんのお話をうかがっていると日本マイクロソフト社の歴史の流れも感じられます。
マイクロソフトには、かれこれ17年間就業しましたね。その後、2005年に、Adeccoに転職しました。Adeccoは、スイスに本社を置く総合人材サービス企業ですが、私が入社した当時の日本法人は、グローバルと言うよりも日本的なカルチャーが色濃かったのを覚えています。当時のアメリカ人のカントリーマネージャーと連携しながら、8年間にわたり、Adecco Japan の制度設計をはじめ、カンパニーカルチャーの変革など、スクラッチから人事・組織改革につとめました。手応えを感じた8年間でしたが、リーマンショックによる経済の落ち込みや、派遣法の変更の影響などダブルパンチを受けて、逆風が吹いたこともあります。汗をかいて耕してきた実感がありますね。

久田さんのリーダーとしての歩みは、平坦な道ではなく、組織の成長や外部環境の変化に伴うダイナミックな変化と共にあったんですね。リーダーとして、どんなことを大切にされてきたのですか。
振り返ってみると、確かに、変革期に呼ばれている気がしますね。
リーダーシップの基盤として、Discipline/ Respect/ Engagement の3つが重要であると考えています。私はラグビーが好きなんですが、イギリスのワールドカップ会場を見ていると、通路にラグビー憲章である「Discipline & Respect」が掲げてあります。ラグビーは、非常に当たりが激しいスポーツですから、特に見えない部分で、いかにDisciplineを保って反則にならないプレーができるか、いかに自分をコントロールすることができるかが重要です。あれだけ当たっておきながらも、お互いにリスペクトを持って、共にプレーするからこそ得られる充実感、つまり「Engagement」は、何にも変え難い。これは、ビジネスの中で大切にしていきたいところです。
Discipline の本質を理解して行動に移すのは、なかなか難しいのではないでしょうか。
「Discipline を自覚する」ということは、自らを律するという意味での「自律」なんです。マネジメントをする立場にあるメンバーには「ルールを作ってコントロールする、定めたルールを守らせるのが、人事やマネージャーの仕事の本質ではない」とよく言ってきました。ルールが無いところや、ルールにはまらない状況下で、責任を持って、自分を律しながら判断し、リスペクトを持って物事を動かしていく。それこそが、よきリーダーやマネージャーのDiscipline を持った行動です。組織において、Disciplineを持って判断できる人材を増やすことは、とても重要だと思います。実現は簡単ではないですが。
組織におけるマネージャーの自律を促すために、どんな取り組みをされたのですか。
各社で、様々な取り組みをしてきましたが、象徴的な例として、Adeccoで報酬制度を変えた時のエピソードがあります。具体的には、ボーナスの支給に関わる制度変更なのですが、この時は、相当の突き上げがありました。大枠のガイドラインは人事側で決めるけれども、各部門ごとに積み上げたボーナスの原資の配分については、各事業部長に任せたのです。事業部長にとっては、重い説明責任が求められる初めての経験だったわけです。なぜこの評価なのか、なぜこの金額なのか、実額をみて手が止まるんですね。
私も覚悟と信念を持って部長たちと向き合い、一貫して、なぜやるのか、人と組織の成長にコミットするということはどういう意味なのかを伝えていきました。部下の立場に立ったら、なぜ、マネージャーはこういう判断をしたのか聞きたいはずです。部下の心が離れていくのは、悪い評価をつけられたからという結果論ではない。説明責任を回避したプロセスに対する不信感からです。2-3年かかりましたが、経験を通してシニアリーダーが育ってくれました。
もう一つの例としては、Adeccoの後に勤めた国際物流の会社で、Flex Time を導入をした時のエピソードがあります。実は、この制度の導入は、社員から歓迎されると思っていたんです。実際、東京の社員は歓迎してくれましたが、意外なことに、関西からは、反対の声があがったんです。その理由を聞いてみると「一部の人間が独占的にFlex Timeを取った時に、周りの人間が不利益を被る。わがままの強い人間のエゴが増長されるので問題!」という想像もしなかったコメントが返ってきました。
毎日、A4一枚くらいのメールを一週間にわたって打ち続けました。「みんなが協力し合って、互いにリスペクトし合って、この制度をいかに良いものにしていくか」ということを、みんなに理解してもらえるまで、しつこいと言われても、自分の言葉で発信し続けました。結果的には、みんなとても喜んでくれました。制度そのものの定着よりも、みんなのためになることを、みんなで作れたという組織のプロセスそのものに意義があったと思います。

現在は、積水フーラー株式会社で、人事・総務のリーダーとしてご活躍されていらっしゃいますが、リーダーの役割をどのように考えていらっしゃいますか。
経営トップと共に、ミッション、ビジョン、GAP(Growth Action Principle)の再定義と、それにそった人事制度の改革を進めているところなのですが、その中で、リーダーの役割について考えさせられることが多々ありますね。積水フーラーは、中間財としての接着剤メーカーですが、今、社内で活性化している議論として「社会とどう接着していくか」というテーマがあります。ESG、CSRの観点から、社会との意義あるコネクション(接着)をつくって、広げていきたいという思いが、社員の中からもわき上がってきています。
リーダーに求められるのは、事業としてのパーパス、社員としてのパーパス、一人ひとりの人生のパーパスを繋げていく役割だと思います。人は、誰しも自分がやっていることに対して、価値を見出したいわけです。価値があると思いたいし、そう思われたい。意味を求めていると思います。社会にどう貢献していくか、それぞれの事業がどう社会と接点を作っていくか、リーダーが言葉にして共有し、そして、自ら行動で示すことも大事だと思っています。
個人レベル、チームのレベル、組織のレベルで、パーパスが共鳴し、社会や世界と繋がっていくというのは、本当に素晴らしいことですね。エンゲージメントも高くなるのではないでしょうか。積水フーラーの社員の皆さんの熱量を感じます。
最近は、MS Teamsを活用して、クラブハウス的な場を毎週水曜日に設けています。週替わりに社員に登場してもらって、カジュアルに話をしてもらうのですが、私は、社員の人となりを引き出すアンカーマンの役回りをしています。仕事しながら聞き流してもらってもいいし、何か質問したいことがあったら自由にジャンプインもできるというプログラムです。
楽しそうですね。まさに、社員との自然な接着を促す番組ですね。
月曜日は、アカデミーと名前をつけてシリーズで展開しています。社内の技術の担当者から話を聞いたり、社長が登場したり、社外からゲストを招いたりしています。マイクロソフトを卒業した仲間たちも、何人かゲストスピーカーとして協力してくれましたね。
最後に、久田さんのパーパスについても、是非お伺いしたいです。
この先、自分が経験として得てきたことのフィードバックをしたいです。言ってみれば「恩返し」でしょうか。人事としての考え方や制度などを「求めている人」のところでお手伝いできればと思っています。
次世代リーダーや、経営者層のメンター的な役割として、久田さんを求める人がたくさんいそうですね。私たちセブンシーズも間違いなくその中に含まれます。今日は、示唆に富んだお話を聞かせていただきました。久田さんという人間力あふれるリーダーと繋がっていることに、感謝しています。

山口浩輝氏(不二製油株式会社 研究開発本部 グローバル市場ソリューション部門)

トヨタコネクティッド株式会社 戦略人事部
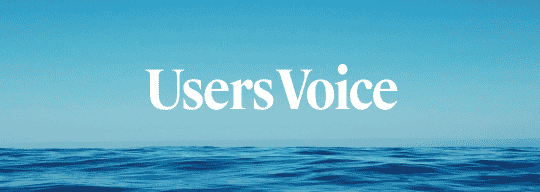
金融系企業 財務部門

林 和明氏(サントリーホールディングス株式会社 デジタル本部 デジタル戦略部 課長)

柏原千英氏(アジア経済研究所 学術情報センター長)

竹内洋二氏(日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 モビリティサービス事業本部長)

早崎達夫氏(積水フーラー株式会社 代表取締役副社長)
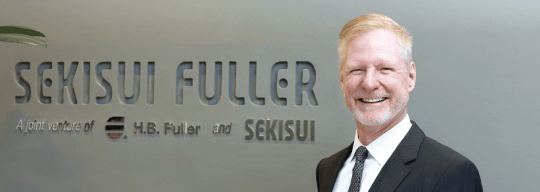
Mr. Scott Pergande氏(積水フーラー株式会社 代表取締役社長)