
Next-Generation Global Talent Program
山口浩輝氏(不二製油株式会社 研究開発本部 グローバル市場ソリューション部門)

『リーダーシップ・ラウンドテーブル』は、グローバルな視野と使命感をもって、長期にわたり、ビジネス・リーダーシップを発揮されているゲストをお迎えし、弊社、揚石洋子と秋吉新平を交えた対談形式で、インタビューさせていただくシリーズ企画です。

今泉氏をお迎えして、以下の3つのテーマでお話をうかがいました。
今泉さんには、日頃から、ビジネスのインスピレーションをいただいています。セブンシーズのマーケティング戦略についてディスカッションした際も、示唆に富んだアイディアやアドバイスをいただき、感謝しています。今日は、MarTech(マーケティング・テクノロジー)業界で、リーダーシップを発揮されている今泉さんの視点やご経験について、あらためてお話をうかがいたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
今泉さんは、ヴァーティカル ジャパンのカントリーマネージャーを務めていらっしゃいますが、着任されて何年になりますか。

ヴァーティカルは、マーケティング・テクノロジーに関わるサービスに特化した専門エージェンシーです。世界最大級の広告代理店グループであるWPPのグループ・カンパニーとして、グローバル企業向けにマーケティング・ソリューションを提供しています。私がカントリーマネージャーを務めて、今年で8期目を迎えます。
着任当時、日本は MarTech の黎明期でした。最近になって、ようやくMarTech業界のグローバル・プレーヤーの勢力図も見えてきていますが、当時は、熾烈なM&Aの真っ只中にあったのを思い出します。
この7年間の変化をどのように捉えていらっしゃいますか。
まさに、時代が動いていると感じます。蒸気機関システムから電力に変わったくらいのテクノロジー変革がマーケティング業界に起こっています。5Gの実用化、クラウドへの移行、ワークスタイルの多様化、サイバー・セキュリティをめぐる課題、仮想通貨の台頭など、産業革命に匹敵するくらいの変化が起きています。
B to Bの流れとしては、営業スタイルの変革が目覚ましいですね。かつて、名刺は営業マンのプロパティだったわけですが、今や会社の資産として扱われるようになりました。また、ここ5年くらいの間に、セールスオートメーションの考え方が普及してきたり、インサイドセールスの役割が注目されるようになってきました。最近では、コロナ禍の影響もあって、フィジカルなイベントや対面式の営業スタイルが、一気にウェビナー形式へと変化しました。
B to Cにおいては、中間流通を通さずにデジタル・チャネルを通じて製品をダイレクトに販売するDirect to Consumerモデルが一気に加速しましたね。それに伴い、個人データ、Cookieデータの扱いをめぐって、GAFAをめぐる独禁法の規制をはじめ、ヨーロッパや中国の個人情報関連法の絡みなど、ビッグデータとして消費者情報が活用されるメリットとリスクの両方で議論を呼んでいます。
この大きな変化の中で、カントリーマネージャーとして、エネルギーを注いでいらっしゃることはどんなことですか。
「エンドユーザーに対して、ファンになってもらえるようなメッセージを、ブランド側がいつ、どう届けるか?」というテーマが、弊社のビジネス領域です。激動のマーケティング戦国時代において、MarTechの投資判断をお客様に働きかけ、お客様のビジネスの未来へとつなげていく、そのガイド役を果たしていきたいと考えています。
ヴァーティカルは様々なマーケティング・プラットフォームをサポートしています。業界では年に数百あまりの新しいプラットフォームが登場しては淘汰されるものもあります。どのプラットフォームのどの機能が優れていて、どのような場面に役立つのかを日々アンテナを張ってアップデートしています。カントリーマネージャーとして、需要の高まりそうなプラットフォームの選定、人材の獲得、資格取得を含めて、日進月歩の業界で、日々最善と思われる意思決定をすることが責務だと思っています。
また、日本における「今」の運用ニーズを注視するのではなく、3年後のコア・コンピテンスが何になるのかについてもアンテナをはり、サービスのどこを研ぎ澄ますべきか戦略的な視点でとらえるようにしています。
デジタル・トランスフォーメーションにおいて、健全な投資判断とは何が決め手になるのですか。
そうですね。私自身が代表として、お客様の経営層と直接、お話することもあるのですが、企業によってDX戦略の判断は分かれますね。自社でeコマースを立ち上げたり、ロジスティクスを握る方向へ舵を切ったり、この先10年を見据えブレークスルーしようと自ら動いている企業は強いです。
詰まるところ、投資判断の要は「データのオーナーシップを企業がどう持つか」ということにつきるのではないかと思います。データのオーナシップについて真剣に向き合っている企業は、確実に競合に対して優位性を高めることができます。そうした企業にとって、MarTechは、ビジネスを支えるバックボーンになります。
一方で、昨今のニュースでも、某メガバンクやコンビニチェーンのテクノロジー導入の失敗例がニュースになっていますが、従来のIT導入の方法ではDXの加速どころか、社会的信用を損なう結果を招きます。このことから企業のDX戦略を経営層がどこまで重要視するかということが注目されます。

ヴァーティカルジャパンの皆さんは、日々どのようなコラボレーションをされているのですか。
社員数でいうと、グローバル全体で1500名なのですが、そのうちの約1000名は、インドのエンジニア・ハブに在籍しています。日本のスタッフにおいては、常時40-50名のインド人のエンジニアと協働しています。また、中国やシンガポールのビジネス・アナリストとの連携も活発に行われています。日々のコミュニケーションを通して感じるのは、ひとくくりで「アジア」とは言えないことですね。本当に多様性に溢れています。
インドと言っても公用語は100以上。北と南で気候も違う。インド人はエンジニアとしての強みが注目されることが多いのですが、実はアーティスティックな才能がある人も多いのです。広告や映画のクリエイティブ・リーダーとして、インド系の人材が数多く活躍しているのもうなずけます。また、インドはヒンズー教の国だと思っていたら、意外とクリスチャンも多く、先日、インドのメンバーが教会に行きたいと言ってきて、少し驚きました。
中華系のメンバーも多数在籍していますが、メインランド、台湾、香港、シンガポールではビジネスのカスタムが全く違いますね。
多様性溢れるチームの中から生まれる化学反応は、ダイナミックですよね。
アジア市場をマクロの視点で捉えると、中国、インド、インドネシアやタイなどのポテンシャルが注目されていますが、その多様性は、イノベーションにつながるビジネスのエネルギーを生み出していると思います。ただ、日本人は、まだ、その多様性のダイナミズムを体感しきれていないかもれません。
多様性を体感するとは、具体的に言うとどんなことでしょうか。
例えば、何か新しい取り組みをスタートしようとする時、アジアのメンバーは、まず「YES!」と言ってから、その先どうしようか、なんとかしようと考えます。圧倒的にポジティブ思考なんですね。
一方で、日本人は「検討します」と言って、石橋を叩き始めます。この時点で日本人は出足が遅れてしまうんです。海外でうまくいった施策を日本で展開しようとする時、日本の担当者は、まずは障害から考えます。未知の世界であればあるほど、その傾向は顕著です。ロジスティクス、納品など、全てを計算してエラーゼロの施策を考えようと努力し、それに多大な時間やコストを費やします。
会議ひとつをとっても、参加者がアクティブに、どうしたら実現できるだろうかとアイディアを出し合っている中で、日本人は、ダメな理由にこだわって、会話に入れないことがあります。日本人は「Try & Error」に慣れていないですし、それが文化的にもよしとはされてこなかったことが影響しているのだとは思いますが、失敗は決してペナルティーではないことを感じとって欲しいですね。むしろ、全てを計算しつくしてからやると、結果的にエッジのない魅力的ではないアイディアになってしまうことが多くあります。アジア諸国のリーダー達と接していると、ビジネスの考え方として、過去を振り返って失敗しても決して戒めない、という習慣があります。DX戦略のようなイノベーションを実現するには、見習うべき考え方だと思います。
システム開発においても、ウォーターフォール開発とアジャイル開発では、時間軸とプロセスが全く異なりますが、最近はリーダーシップの分野でもアジャイル型の意思決定が求められるようになってきています。例えば、15分の時間枠の中で、多国籍で形成されたチームのディスカッションを活性化させ「Optimal Conclusion」(最適解)に至るプロセスをマネージする。また、そうした会議体でのモデレーションのスキルもリーダーに問われます。
この15分というのは、相当密度が高そうですね。社内で何かトレーニングを行っているのですか。
月に1回、社内でプレゼン・コンテストを実施しています。旬なトピックに対して、二人組で5分のプレゼンを行ってもらうのですが、単にプレゼンテーション・スキルを磨くのではなく、「ブレインストーミング X ロジカル・シンキング X プラニング X プレゼンテーション・スキル」を掛け合わせた総合力を鍛えるのが狙いです。コンテスト形式にこだわっているのは、ビジネスの現実を意識してのこと、お客様に選ばれなければ、売り上げには結びつきません。勝つ!経験というのも大事なんですね。
このトレーニングを継続したことで、社員の戦力レベルは格段に上がってきています。既にビジネス・リターンが出ていますよ。社員が育って活躍する姿を目にするのは嬉しいですし、本人も会社も共に成長するエコシステムは重要だと思います。

今泉さんのご経験から、グローバルにわたり合っていくために、日本人は、どんな力を鍛える必要があるのでしょうか。
そうですね。日本人は、一般的に嫌われないための処世術を優先していると感じます。根回しの文化や、コンセンサスを重んじる教育も受けているわけですが、それが行き過ぎると、アジリティーが求められるイノベーションの時代においては、グローバルのスピードについていけなくなったり、アウトプットの質が低くなってしまいかねないということを意識する必要があります。
先日、某企業のシニアマネジメント向けにワークショップを実施しました。テクノロジーの投資判断に関わるヒアリングを行い、1時間のワークショップ形式でクリエイティブなアイディアを出していく場だったのですが、参加者の一人が突然「今、何をやっているかわからないんですけど」と言って、一緒に参加している10人のブレインストーミングを止めてしまったんです。参加型の打ち合わせ形式は不慣れだったのでしょう。自分の快適ゾーンには無い未知のやり方に飛び込むことができず、パニックになってしまったんですね。その時、私は、ファシリテーターとして、主体的に参画してくれている方々のアウトプットを止めるべきではないと判断しました。タフな役回りではありますが、わからないと言い続けた一人の参加者を制する強さが求められる場面でしたね。
実は、グローバル環境では「足を引っ張る圧力や、イノベーションを妨げる因子」を放置せずに、適切にマネージしていくということも、リーダーとしてやらなければなりません。こういう強さをどう鍛えるか、日本の学校では、なかなか教えてくれないことですね。
まさに、グローバルにわたり合っていく力が試されるエピソードですね。
日本人は、未知の体験や、違いに対して免疫をつけていく必要がありますね。多様なカルチャーに対して「違い」を楽しむ感覚を持てるようになるといいですね。そして、できない理由や問題をリストアップして検討し続けるのでなく、まずはどんどん挑戦した方がいい。イノベーションが生まれる場では、たとえ上手くいかなかったとしても「だから言ったじゃないか」とか「I told you!」とか言われることはない。もう、そういう時代では間に合わないし、ビジネスにおいても、新たな時代が始まっていると思います。
従来の日本の教育では、「ラーニング」と「イノベーション」が、意図せずに別物として扱われてきた傾向がありますが、今泉さんは、イノベーションを引き寄せるラーニングの仕組みを自らデザインし、社員教育やクライアントの啓蒙の場で実践されていらっしゃるんですね。私たちセブンシーズとしても、大いに刺激を受けました。今日はどうもありがとうございました。

山口浩輝氏(不二製油株式会社 研究開発本部 グローバル市場ソリューション部門)

トヨタコネクティッド株式会社 戦略人事部
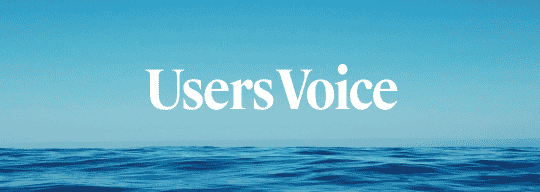
金融系企業 財務部門

林 和明氏(サントリーホールディングス株式会社 デジタル本部 デジタル戦略部 課長)

柏原千英氏(アジア経済研究所 学術情報センター長)

竹内洋二氏(日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 モビリティサービス事業本部長)

早崎達夫氏(積水フーラー株式会社 代表取締役副社長)
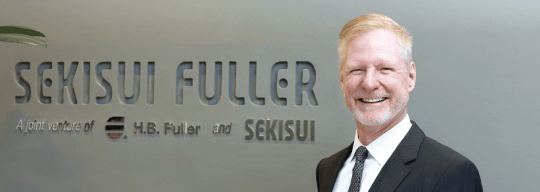
Mr. Scott Pergande氏(積水フーラー株式会社 代表取締役社長)