
Next-Generation Global Talent Program
山口浩輝氏(不二製油株式会社 研究開発本部 グローバル市場ソリューション部門)

『リーダーシップ・ラウンドテーブル』は、グローバルな視野と 使命感をもって、長期にわたり、リーダーシップを発揮されているゲストをお迎えし、弊社、揚石洋子と秋吉新平を交えた対談形式で、インタビューさせていただくシリーズ企画です。

アジア経済研究所学術情報センター長 柏原千英氏をお迎えして、以下の3つのテーマでお話をうかがいました。
日本貿易振興機構(JETRO)アジア経済研究所の学術情報センター長でいらっしゃる柏原さんをゲストにお招きすることができて、大変嬉しく思っております。弊社は、研修プログラムのご提供を通して、海外に赴任するビジネスリーダーの方々の支援をさせていただいております。是非、今日は、アジア地域のスペシャリストである柏原さんのご経験から、多くを学ばせていただきたいと思っております。まず、学術情報センターについて教えてください。私たちにとっては、アカデミックで敷居が高そうなイメージがあります。
学術情報センターの機能は、図書館、出版、研究所ウェブサイト運営の3本柱です。図書館は、実はとてもオープンなんですよ。組織名に「アジア」とありますが、開発途上国に関する図書・統計・新聞・雑誌・マイクロフィルムなど、約80万点にのぼる資料の管理と利用促進を行っており、4階建ての図書館は全館開架式で予約不要、国内外どなたでもご利用いただけます。京葉線海浜幕張駅から徒歩10分弱ですので、ぜひ一度、ご来館ください。
そうなんですか!柏原さんのお話しを聞いて、世界規模の知的アセットを所蔵する「アジ研・学情センター」(アジア経済研究所・学術情報センター)が一気に身近に感じますね。
資料のご利用者は、途上国研究を専門とする国内外研究者はもとより、そのタマゴである学部生、大学院生、そして、ビジネス進出や市場拡張に関連する知見を求めるビジネス・パーソンなど、多岐にわたります。教授がご担当のゼミ生を連れて、あるいは海外の政府機関や研究所の方々が大人数で来館されることもありますし、近年では逆に、大学や高校に出向いて利用方法や所蔵資料の紹介もしています。
アジ研は1960年の設立当初から一貫して、途上国研究と資料収集を継続してきました。その成果をもとに、日本の経済・社会・外交政策の策定や方針転換、法制度の整備や、世界情勢や産業構造・生産ネットワークの変化が日本経済に与える影響など、専門的な知見を提供する重要な役割も担っています。収集面での例を挙げると、本国では既に喪失した官報やセンサス等のデータ類、ジャーナルなど、超長期にわたるシリーズ資料がズラッと所蔵されているのを目にして、その国の政府関係者に驚かれることもあります。また、一言で学情センターの役割を表現するならば、「研究所の研究成果の社会への出口」です。研究成果が多方面で活用されることが公的機関としての使命ですので、オープンアクセス方針に基づき、原則として即時公開しています。公開時の制約を最小に、誰もがアクセスしダウンロードできるようなサイトや機関リポジトリ運営をするとともに、POD(print on demand)により「本」へのニーズにも対応しています。今年(2025年)は、復刻リクエストをいただいている途上国の衣食住や生活に関するエッセイ集シリーズ全7冊を再公開します。
65年にわたるアジ研の歴史と共に、学情センターの存在意義は本当に大きいですね。
当館の特徴は、現地語の習得がマストとなる地域担当制に加え、国立国会図書館や様々な専門図書館、大学図書館、研究機関とのネットワークを駆使した情報提供が可能な点にあります。所蔵資料のみならず、政治・社会情勢にも通じた頼りになるライブラリアン揃いのうえ、リサーチ内容や深掘り度に応じて他館の情報や所内の研究者にもお繋ぎしますので、Eメールフォームからご相談ください。
幅広くも深くも相談できるのは、まさにプレミアム・サービスですね。情報の海の中で迷子になって諦めてしまうことも多々ありがちなんですが、学情センターを含む研究所のプロフェッショナルな皆さまに相談ができるのは、本当に心強いです。アジア諸国や開発途上国に赴任される企業リーダーに、是非、おススメしたいと思います。
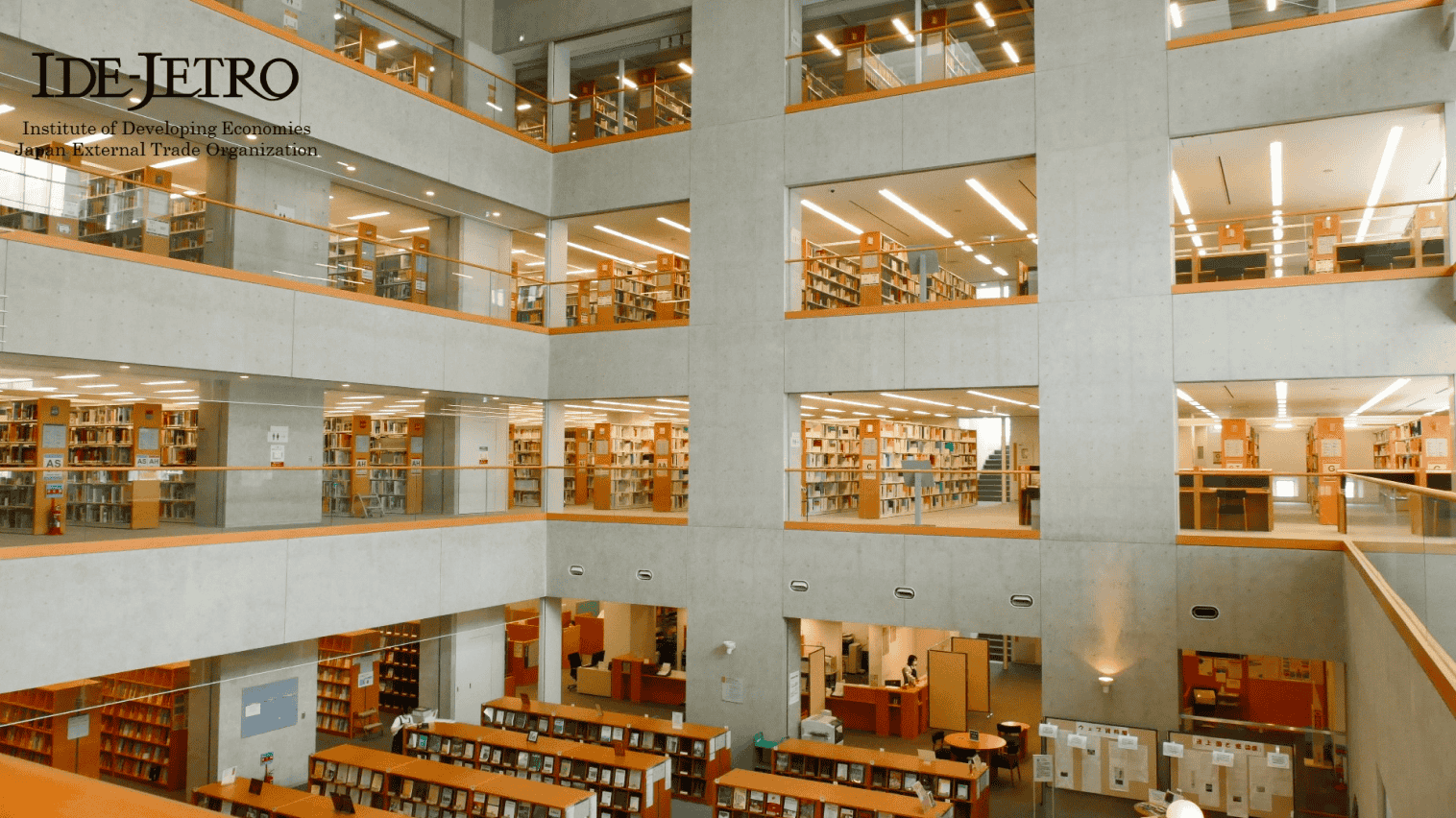
柏原さんのキャリアについて、おうかがいさせてください。
大学・大学院では、社会科学のなかでも国際法や国際機構論を中心に専攻したのですが、学卒で社会人デビューする時に、「まずは足元の日本から理解しよう。銀行であれば、経済・社会全体が俯瞰できるはずだ」と考え、民間のメガバンクに入行しました。当時の自分の発想は、今思うと大雑把極まりないですね。
グローバルな視野を持つためには、まず日本の社会や経済を理解することが必須だという考え方は、柏原さんのキャリアの原点となっているのではないでしょうか。銀行にお勤めになっていた頃のご経験は、現在の柏原さんの価値観に、どんな影響を与えていますか。
現在の職場でも勤続約30年になるので、民間での現場経験は遠い昔ではあるものの、バブル経済最終期のエピソードとして、強烈に記憶に残っています。当時、私はディーリングルームに勤務していたのですが、数十銭の為替レート差や1/8%、1/16%の金利差の価値の大きさ、取引の成否を分ける1分、2分という時間軸に囲まれ、電話の向こうにいる顧客の需要にいかにスピード感をもって応えるかという緊張が常にありました。特に、市場動向や相場見通しなど、情報サービスの質とスピードの両方を追求し続けることの厳しさについては、かなり刷り込まれましたね。この刷り込みが現職に就いてから時々フラッシュバックするのは、即断力を必要とする時でしょうか。
日本の公的機関と民間ビジネス両方のご経験を融合されていらっしゃるんですね。
海外でお仕事の経験をされたのはいつ頃でしたか。
アジ研に入って5年目くらい、私自身は30代半ばでした。アジア通貨危機の数年後で、アジア開発銀行(ADB)へアサインメントの機会を得てフィリピンのマニラに2年間駐在し、対フィリピン政府案件のチームで、融資が効果的に活用されるためのオペレーション・マネジメントと一連のテクニカル支援を担当しました。具体的には、政府職員や金融とその関連業界が対象の、企業統治の概念を入れた銀行部門改革、証券市場の振興政策、会計制度や監査・監督の強化などをテーマとする研修です。多国籍編成のコンサルタントを含むADB内外の様々なステークホルダーと共に、縦割りの専門分野に横串を通すイメージでの取り組みが必要なプロジェクトですね。
フィリピンという一国の経済を左右するお仕事ですね。
当時のフィリピンは、当初は軽微だと考えていた危機の影響―銀行の営業停止や株式・債券市場の停滞と財政困難―が深刻化し、近隣諸国に遅れをとった対応策の実行が喫緊の課題でした。そこでADBが制度インフラの整備を条件に融資を実行したのですが、清算銀行の資産整理を迅速に行うための法案審議の進行具合を横目に、クライシスからの脱却や再建プロセスをどのようにハンドルすべきなのか、証券取引委員会や中央銀行などの金融監督機関と議論しながら進めるという、かなり濃い経験をしました。ドタバタぶり?をこちらに書いています。
ご苦労も多かったと思いますが、ご担当されたプロジェクトの意義やインパクトは、本当に大きいですね。
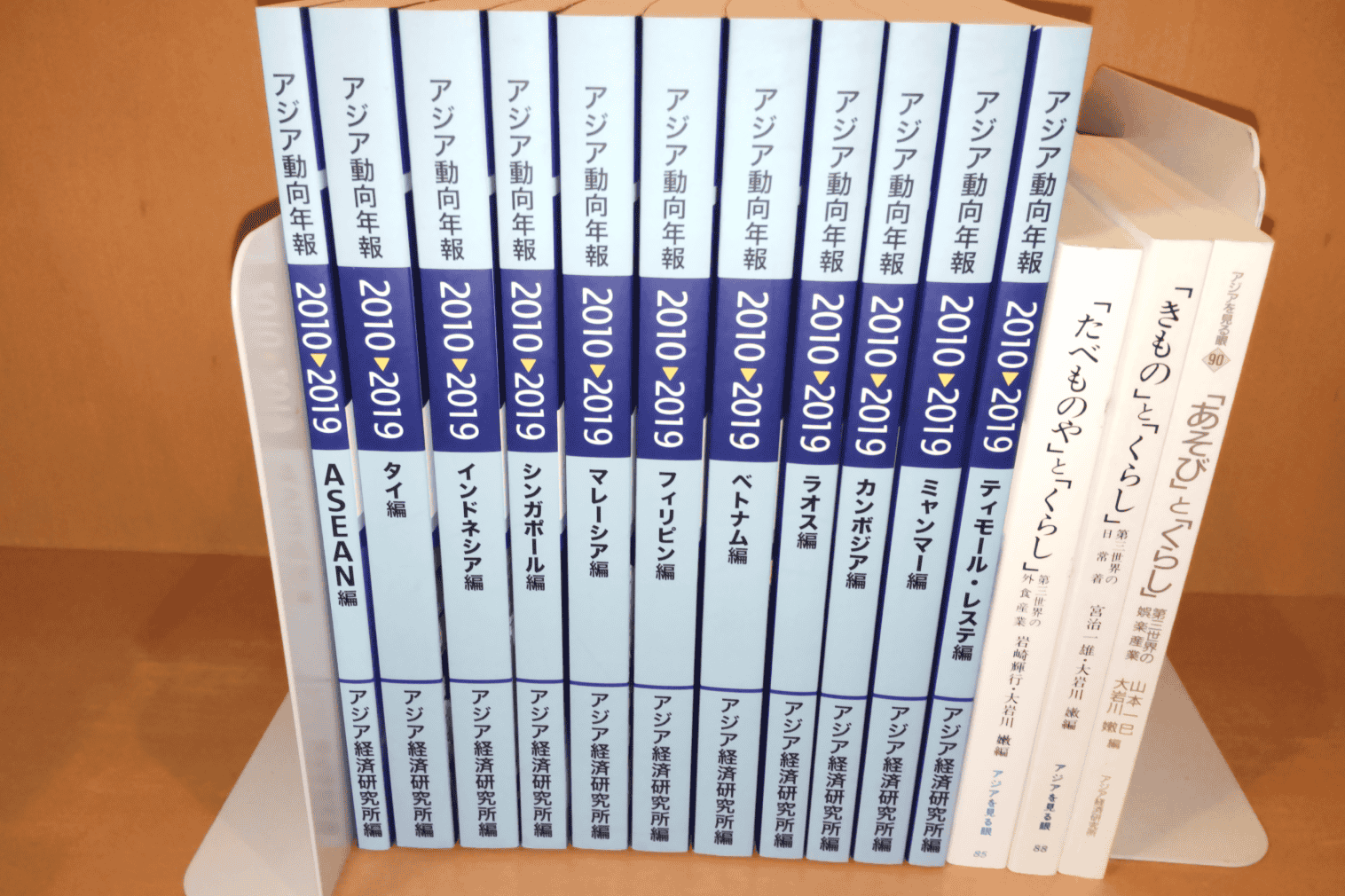
アジア各国の10年が1冊にまとめられた動向年報バンドル版(通称、一部)と復刻予定の書籍(一部)
弊社では、海外赴任前の日本のビジネス・リーダーの方々向けに「Acclimatization:早期順応」に特化した研修プログラムをご提供していますが、とりわけ、リーダーの「発信力」の強化には力を入れています。
確かに、日本人は発信が少し苦手かもしれませんね。片やフィリピン人は、アピール上手でアウトプット盛りまくり!何かを得る機会は逃さない!と積極的です。典型的日本人だった私も、プロジェクト発足後数カ月ほど経ったところで、ストレス負けによる激しい胃痛に悩まされました。自分から言葉を発しない限り、プロジェクトの本来目的から逸れる事態になりかねないと気付いたからです。そこで、実行側の意図と理由を表すキーワードを多用し、とにかく伝えることが肝心なのだと切り替えました。そして、言葉にするからには一方的ではなく、お互いの意図を「理解」し合うことが、何より重要だと考えるようにしました。
柏原さんのおっしゃる通り、意図や目的を伝える情熱は、本当に大事ですね。流暢な英語を習得しようというモチベーションとは全く別次元の「グローバル・コミュニケーションの本質」をとらえていらっしゃると思います。
母語ではない言語で意思疎通するには、「単語族」を脱するレベルの習得は必要でしょう。英語はグローバル言語のひとつではありますが、第一言語や母語とする国は地球上の多数派ではありません。どこでも一律同じではなく、発音や言い回しに国や地域のローカル色が反映されて、誤解や話のネタにもなります。それでも、理解しよう、されようと使うならば、「通じ」ます。私は、英語は特定の国の言語ではなく、世界の人々がお互いに歩み寄って使っている、歩み寄るために使う言語、ツールなのだと思っています。
お互いが歩み寄って語る言葉という表現は、本当に素敵です。柏原さんのお話しから、グローバルとローカルを掛け合わせた「グローカル」なコミュニケーションを大切にする価値観を感じます。これからアジア諸国に赴任されるリーダー向けに、メッセージをいただけますでしょうか。
歩み寄り言語と意思疎通するマインドを第一のベースとするなら、知識武装は第二のベースです。ご赴任前に過去25年程度の経済/社会/産業構成、政治体制、対外関係の大まかな変化をインプットしておくと、状況判断の大きな助けになるでしょう。また、「何も知らずには来てませんよ」アピールにも使えます。これらの上に拠って立てば、ビジネス戦略はより盤石になるのではないでしょうか。アジ研の研究成果や図書館は、リーダーとして重責を担われる方々の課題解決や意思決定につながるリサーチに、知見と情報面から貢献いたします。アジア地域のみならず、中近東、アフリカ、中南米、南アジアなども同様です。ぜひ、ご活用ください。
今日は、貴重なお話をありがとうございました!


山口浩輝氏(不二製油株式会社 研究開発本部 グローバル市場ソリューション部門)

トヨタコネクティッド株式会社 戦略人事部
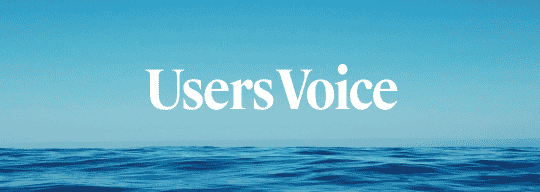
金融系企業 財務部門

林 和明氏(サントリーホールディングス株式会社 デジタル本部 デジタル戦略部 課長)

柏原千英氏(アジア経済研究所 学術情報センター長)

竹内洋二氏(日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 モビリティサービス事業本部長)

早崎達夫氏(積水フーラー株式会社 代表取締役副社長)
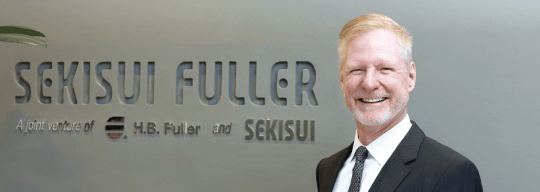
Mr. Scott Pergande氏(積水フーラー株式会社 代表取締役社長)